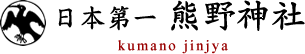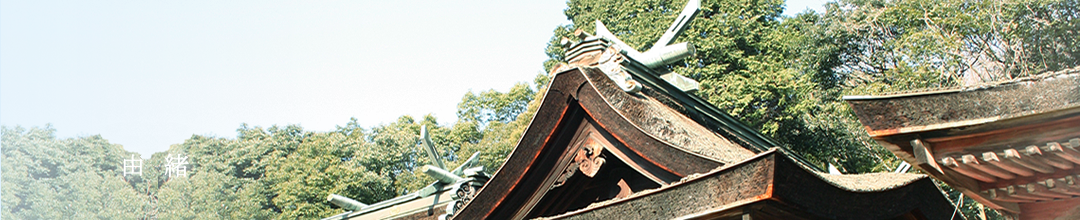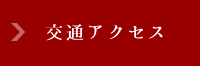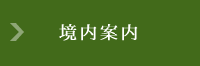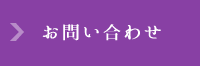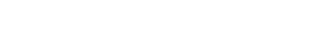熊野神社の由緒
 西暦六三四年、役行者(役小角)は茅原(ちはら)の里、奈良県南葛城郡葛城村に生まれ、当時の仏教とは違い、直接、民衆を救い、自分も修行をしていくという宗教観を持っていました。紀州、熊野大峯の山々で修行を重ね、修験道の開祖となりました。
西暦六三四年、役行者(役小角)は茅原(ちはら)の里、奈良県南葛城郡葛城村に生まれ、当時の仏教とは違い、直接、民衆を救い、自分も修行をしていくという宗教観を持っていました。紀州、熊野大峯の山々で修行を重ね、修験道の開祖となりました。
ところが、役行者が民衆を惑わすという罪で伊豆大島に流され、高弟たちは紀州熊野の十二社権現の御神宝を奉じて瀬戸内海に逃れ、四国九州に浄域を求めた後、児島の柘榴浜に上陸し、熊野道といわれている山道を通り、大宝元年(701)三月三日、福岡の里と呼ばれていたこの地に鎮座祭典をし、それが、現在の春のお祭り(五月十八・十九日)です。
 天平十二年(740)、聖武天皇は児島一円を本宮の御神領として寄進しました。現在地に社殿を建立したのが始まりです。
天平十二年(740)、聖武天皇は児島一円を本宮の御神領として寄進しました。現在地に社殿を建立したのが始まりです。孝謙天皇紀(749-758)には、紀州熊野権現に対して日本第一の称が与えられ、当社もその号を称することになりました。
承久の乱(1221年)に敗れた後鳥羽上皇は、隠岐に配流され、その第四皇子で、鎌倉幕府第四将軍になる候補であった冷泉宮頼仁親王は、この地に配流されました。また、弟の桜井宮覚仁親王は乱を恐れ、この地に赴任し尊瀧院の住職となりました。公卿山伏といわれる由縁です。
 応仁の乱(1469)で開幕となった戦国時代の兵火のため、社殿をことごとく焼失してしまいました。
応仁の乱(1469)で開幕となった戦国時代の兵火のため、社殿をことごとく焼失してしまいました。明応元年(1492年)、社殿は天誉長老により再建されました。国の重要文化財に指定されている第二殿が、その時建立されたものだといわれています。以後、復興を見ますが、次第に社領は減少し、中国管領大内義興、毛利家父子の守護を受けましたが、児島一円の領地はわずか三ヵ村に減ってしまいます。
西暦1600年代半ば、池田光政公により、吉備津彦神社の大守家から神官が赴任され、祭祀を専らにさせるなど、あつい保護の下に明治に至りました。
 慶応四年三月(1868)、神仏分離(神仏判然令)により、現在は、宗教法人熊野神社、宗教法人修験道五流尊瀧院と呼ばれています。
慶応四年三月(1868)、神仏分離(神仏判然令)により、現在は、宗教法人熊野神社、宗教法人修験道五流尊瀧院と呼ばれています。
平成十五年(2003)九月二十一日、所有の熊野神社長床拝殿を焼失しましたが、五流尊瀧院の寛大な配慮により、再度、氏子や近在の崇敬者により拝殿が再建されました。
熊野神社御祭神
| 主祭神 |
|
境内神社御祭神
| 火産霊命 |
| 素戔鳴命 |
家津御子大神
| 大綿津見神 |
| 市杵島姫命 |
| 倉稲魂命 |